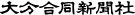全国・海外ニュース/ スポーツ
勝敗は最後の笛が鳴るまで分からない。これは確かにサッカーの真理であろう。しかし、その後の展開が早々に読めてしまう試合もたまにはある。それが、マラカナン競技場(リオデジャネイロ)で行われた準々決勝のフランス対ドイツだったのではないだろうか。
両国がW杯で対戦するのは、今回で4度目。初対戦となった1958年スウェーデン大会の3位決定戦で勝利して以降、フランスはW杯でドイツに勝てていない。
ともにW杯優勝国ながら、フランスは「ドイツ・アレルギー」を抱いているように見える。その発端となったのが、82年スペイン大会。準決勝で西ドイツ(当時)と激突したフランスは延長戦の前半途中で3―1とリードしたものの、追いつかれる。そして、W杯では初めてとなったPK戦で涙をのんだ。まさかの結末は、トラウマとなって今もフランスを苦しめているのだろうか。
ドイツが「フランスはカモ」の“方程式”をより強めたのは、86年メキシコ大会。またも準決勝でフランスと相対したドイツは前半9分に先制すると、攻めに出る相手守備ラインの裏を突き、終了直前に追加点。フランスをいたぶる快感を身につけたのだ。
先制されたら追いつけない。先制しても追いつかれる。そんな強豪らしからぬ心理で、戦いに挑んだわけでは決してないだろう。ただ、試合開始から良い形の攻めを展開し、主導権を握ったかに見えていたフランスにとって、前半13分にFKからフンメルスにヘディングをたたき込まれたのは、かなりショックだったに違いない。しかも、それはドイツに訪れた初めてのチャンスだったのだ。
その後、フランスは確かに攻め込んだ。ただし、それはサイドまで。いくらクロスを入れても、センターバックのボアテングとフンメルスがことごとくカットする。ようやく決定機を作っても、大会最高のGKノイアーがシャベルのような手でいとも簡単にストップ。そんな光景を目の当たりにしたフランスの選手たちに「今回も無理か」との感情が芽生えたとしても、致し方のないことだった。
インフルエンザの影響で、ドイツが万全でなかったのは明らか。それでも手堅く勝つのが、この国の持つ伝統なのだろう。一方、フランスはというと、ドイツに対する苦手意識だけが強まる1戦になってしまった。
岩崎龍一[いわさき・りゅういち]のプロフィル
サッカージャーナリスト。1960年青森県八戸市生まれ。明治大学卒。サッカー専門誌記者を経てフリーに。新聞、雑誌等で原稿を執筆。ワールドカップの現地取材はブラジル大会で6大会連続となる。
スポーツ一覧
7月05日
- 【W杯コラム】遠かった勝利 07/05 12:49
- ダルビッシュ勝敗付かず 07/05 12:41
- 【W杯コラム】不安な王国攻撃陣 07/05 11:51
- 川崎は4打数2安打 07/05 10:40
- ゴルフ、63のハーリーが首位 07/05 10:12
- テニス男子、中川組が準決勝進出 07/05 09:32
- テニス、フェデラー決勝へ 07/05 08:54
- W杯、アルゼンチンなど会見 07/05 08:39
- ブラジル2―1コロンビア 07/05 07:51
- フランス0―1ドイツ 07/05 03:45
- テニス、ジョコビッチが決勝へ 07/05 00:32
7月04日
- ソ3―2楽(4日) 07/04 21:50
- 広7―1ヤ(4日) 07/04 21:21
- 柿谷「移籍は自分なりに考える」 07/04 19:42
- 体操、内村が全日本種目別欠場 07/04 19:37
- 勝負強いアルゼンチン 07/04 17:57
- 和田が3A球宴に選出 07/04 16:09
- 川崎は無安打2四球 07/04 13:15
- テニス、アクセサリーも白に規定 07/04 11:57
- 五輪会場「間に合う」とリオ市長 07/04 10:58
- 米男子ゴルフ、ブリクストが首位 07/04 10:26
- 陸上、ゲイが9秒93で2位 07/04 10:06
- ダルビッシュ、5日に先発変更 07/04 09:55
- テニス、松村・山崎組2回戦敗退 07/04 09:22
- テニス、クビトバ3年ぶり決勝へ 07/04 00:31
7月03日
- テニス、中川は3回戦敗退 07/03 23:28
- 西3―8日(3日) 07/03 22:05
- オ7―4楽(3日) 07/03 21:40
- ソ7―0ロ(3日) 07/03 21:26
- 川内、6日に豪州でマラソン出場 07/03 20:01
- 体操の白井「切符つかみたい」 07/03 19:12
- 柿谷のスイス移籍でC大阪が説明 07/03 18:36
- 長谷部がW杯「熱い声援に感謝」 07/03 17:16
- 稀勢の里「10代より充実」 07/03 16:57
- 野球部監督が部員平手打ち 07/03 16:29
- ドイツにタレント豊富 07/03 15:17
- 【W杯コラム】激戦続きの決勝T 07/03 13:41
- 中止のプロ野球 07/03 13:31
- 田沢は1/3回を2失点 07/03 12:51
- 空気銃所持の年齢条件緩和へ 07/03 11:05
- バスケ日本が8強入り 07/03 09:57
- オランダのロッベン、初Vに意欲 07/03 09:42
- テニス、松村・山崎組が2回戦へ 07/03 09:22
- イチロー無安打、チーム5連敗 07/03 08:46
- フェデラー、逆転勝ちで4強入り 07/03 08:45
- W杯準々決勝へブラジルなど調整 07/03 08:06
- イチローは3打数無安打 07/03 06:22
- 川崎は4打数無安打 07/03 05:05
- 八百長疑惑報道で資料提供求める 07/03 01:41
- 小林可夢偉のケータハム売却 07/03 00:32
- 柿谷曜一朗、バーゼル移籍濃厚 07/03 00:29
7月02日
- 西6―5日(2日) 07/02 22:36
- オ0―2楽(2日) 07/02 22:13
- テニス女子、青山組は3回戦敗退 07/02 21:55
- ソ6―1ロ(2日) 07/02 21:47
- 広4―3巨(2日) 07/02 21:30
- 高校硬式部員、初の17万人超え 07/02 20:01
- 競泳ロンドン銅の上田さん結婚へ 07/02 18:53
- J2千葉の関塚新監督が抱負 07/02 18:38
- JOCが就職支援アスナビ説明会 07/02 18:32
- 高校野球、来春も32校が出場 07/02 17:36
- 楽天、大久保2軍監督が1軍指揮 07/02 16:43
- ヤンキース田中将は4日に先発へ 07/02 14:01
- マリナーズ岩隈が6勝目 07/02 13:48
- 【W杯コラム】エース復活に期待 07/02 13:04
- レッドソックス上原が2敗目 07/02 12:44
- ヤンキースの黒田が6敗目 07/02 12:03
- 【W杯コラム】散歩する王様 07/02 11:36
- W杯8強は欧州4、南米3 07/02 10:32
- ベルギー2―1米国 07/02 08:38
- 全英テニス、ナダルが4回戦敗退 07/02 08:34
- 川崎は3打数1安打 07/02 05:59
- アルゼンチン1―0スイス 07/02 04:22
7月01日
- オ8―5楽(1日) 07/01 22:24
- 広7―8巨(1日) 07/01 22:19
- 競泳で北京銅の佐藤が引退 07/01 22:01
- 西2―4日(1日) 07/01 21:43
- 解任不服とし自転車競技連盟提訴 07/01 21:16
- ソ0―1ロ(1日) 07/01 21:13
- サッカー、原専務理事に人選一任 07/01 19:39
- 北島が福島など3市で水泳教室 07/01 18:45
- 関塚隆氏、J2千葉監督に 07/01 18:12
- JOC、選手強化費の実態初調査 07/01 15:52
- ザッケローニ監督が帰国の途に 07/01 13:33
- 【W杯コラム】体力差縮まり苦戦 07/01 13:14
- イチローは3打数無安打 07/01 13:07
- 【W杯コラム】何かを起こす予感 07/01 11:57
- ウルグアイ大統領がFIFA罵倒 07/01 09:55
- ドイツ2―1アルジェリア 07/01 08:44
- クルム伊達組、2回戦敗退 07/01 08:15
- スアレスが「かみつき事件」謝罪 07/01 05:04
- フランス2―0ナイジェリア 07/01 03:52
6月30日
- 相撲、大砂が上位挑戦「楽しみ」 06/30 21:36
- 五輪組織委、競技団体に協力要請 06/30 20:03
- リビウ、22年冬季五輪招致撤退 06/30 19:13
- 全柔連、13年度の赤字決算承認 06/30 18:21
- 宮城県、羽生選手を「絆大使」に 06/30 16:45
- 命運握るメッシとシャキリ 06/30 16:42
- ゴルフ、松山は14位のまま 06/30 15:51
- 術後休養中の星野監督が球宴辞退 06/30 13:28
- 上原が18S、田沢無失点 06/30 13:16
- 【W杯コラム】素晴らしき敗者 06/30 11:46
- 白鵬、史上3人目の大台へ 06/30 11:28
- ローズがプレーオフ制し6勝目 06/30 10:22
- ドイツ監督「気合十分」 06/30 09:56
- 米女子ゴルフ、野村が31位 06/30 09:29
- コスタリカ、PK戦制す 06/30 08:41
- アギレ氏が日本新監督と報道 06/30 08:16
- Bジェイズ川崎は2打数無安打 06/30 05:23
- オランダ2―1メキシコ 06/30 03:34
- W杯観戦中に心筋梗塞、死亡 06/30 00:54
6月29日
- J1柏の田中、スポルティングへ 06/29 23:50
- 棒高跳びイシンバエワが女児出産 06/29 23:04
- サッカー、福島などJ3勢代表に 06/29 21:49
- フットサル名古屋、大分が2連勝 06/29 19:27
- 女子ゴルフ、酒井がツアー初優勝 06/29 17:47
- フランスに主導権、独優位 06/29 17:42
- 女子ゴルフ、16歳蛭田が初優勝 06/29 17:35
- 柔道、東海大が最多更新の7連覇 06/29 17:22
- D5―7広(29日) 06/29 17:08
- 西3―7ソ(29日) 06/29 16:42
- 日2―3楽(29日) 06/29 16:25
- ロ2―1オ(29日) 06/29 16:24
- オランダがメキシコと対戦 06/29 16:22
- W杯がNBA、大リーグ上回る 06/29 15:17
- 中止のプロ野球 06/29 13:41
- 【W杯コラム】大会救った勝利 06/29 12:18
- 【W杯コラム】瞬時に完璧な判断 06/29 11:57
- Rソックス上原が17セーブ目 06/29 11:32
- 米男子ゴルフ、リードが単独首位 06/29 11:25
- J2京都、新監督に川勝氏 06/29 11:12
- バスケU―17、日本は黒星発進 06/29 10:01
- 米女子ゴルフ、宮里美1アンダー 06/29 09:46
- 全英ジュニア、松村は1回戦敗退 06/29 08:58
- 「ブラジル戦に爆弾」と偽情報 06/29 08:42
- コロンビア2―0ウルグアイ 06/29 08:28
- 「かんでない」と厳罰スアレス 06/29 08:09
- 川崎は1安打1打点 06/29 05:55
- ブラジル、PK戦制す 06/29 05:20
- 全英テニス、ナダルが4回戦へ 06/29 00:30
6月28日
- C大阪、ミャンマーで交流 06/28 23:04
- J2首位湘南、北九州に快勝 06/28 22:14
- サッカー、朴智星氏がOB戦出場 06/28 20:43
- 卓球、14歳平野美がア大会代表 06/28 20:28
- 柔道、山梨学院大が最多5度目V 06/28 19:48
- 野球BCリーグ、群馬が前期優勝 06/28 19:44
- 四国リーグ、徳島が前期優勝 06/28 18:51
- 速攻の蘭、パスのメキシコ 06/28 18:50
- 女子アマゴルフ、佐藤らが決勝へ 06/28 18:36
- ゴルフ、酒井と全美貞が首位並ぶ 06/28 18:30
- D7―4広(28日) 06/28 17:59
- 西8―6ソ(28日) 06/28 17:52
- 日2―1楽(28日) 06/28 17:41
- ロ3―4オ(28日) 06/28 17:33
- フットサル、名古屋が初戦快勝 06/28 16:42
- バレー、日本は独に敗れ11連敗 06/28 16:41
- W杯、アルゼンチンとの衝突警戒 06/28 15:48
- 森重「悔しさ忘れずに」 06/28 15:45
- Bジェイズの川崎は2安打1得点 06/28 12:18
- イチローは4打数無安打 06/28 11:17
- 羽生の来季は中国杯とNHK杯 06/28 10:31
- 米男子ゴルフ、ウッズが予選落ち 06/28 09:52
- アンディ・マリーが4回戦へ 06/28 08:43
- W杯、地元ブラジルが最終調整 06/28 08:13
- 韓国、洪明甫監督に不満噴出 06/28 05:43
- FIFA、スアレスに「治療を」 06/28 01:41
- ベッケンバウアー氏が復権 06/28 01:39
- フィギュア羽生が来季SP初披露 06/28 00:19
- 東京五輪、ラグビー会場変更も 06/28 00:02
6月27日
- 青山組、ウィンブルドン3回戦へ 06/27 22:11
- W杯敗退の韓国で監督に不満噴出 06/27 22:07
- 日2―7楽(27日) 06/27 21:45
- 北島康介が都水泳協会理事に 06/27 21:38
- D0―6広(27日) 06/27 21:31
- ロ0―6オ(27日) 06/27 21:29
- 西3―1ソ(27日) 06/27 21:11
- 女子ゴルフ、アン・ソンジュ首位 06/27 20:11
- レスリング世界王者がドーピング 06/27 20:08
- 東京マラソンに準エリートの部 06/27 19:37
- フットサル、初参戦の仙台ドロー 06/27 19:34
- ゴルフ、勝ら10代が8強占める 06/27 19:30
- サッカー協会会長「申し訳ない」 06/27 18:49
- 都知事、競技団体に協力呼び掛け 06/27 18:43
- 男子ゴルフ、甲斐が逆転優勝 06/27 16:59
- ゴルフ、白浜が62で首位発進 06/27 16:57
- ネイマール好調なブラジル 06/27 16:46
- 交流戦MVPに巨人・亀井 06/27 15:47
- IOC、五輪会場見直しに理解 06/27 13:09
- 【W杯コラム】出場枠の見直しも 06/27 12:42
- ブルージェイズ川崎1安打1得点 06/27 11:33
- NBAのドラフト会議開く 06/27 11:19
- 復帰のウッズは83位と出遅れ 06/27 10:07
- 米ゴルフ、宮里藍らが最終調整 06/27 08:44
- テニス、フェデラーは3回戦へ 06/27 08:29
- 韓国0―1ベルギー 06/27 08:05
- アルジェリア1―1ロシア 06/27 07:47
- ポルトガル2―1ガーナ 06/27 03:49
- 米国0―1ドイツ 06/27 03:35
- W杯、ガーナが主力2人を追放 06/27 00:00
6月26日
- ウルグアイFWスアレス出場停止 06/26 23:43
- 錦織、ウィンブルドン3回戦へ 06/26 21:45
- D2―1日(26日) 06/26 20:56
- 18歳権藤が首位で決勝Tへ 06/26 20:53
- 女子ゴルフ、アン首位で酒井2位 06/26 19:29
- 柔道、初の女性評議員が誕生 06/26 18:31
- 湾岸部の五輪会場予定地を視察 06/26 17:50
- ザック日本、帰国の途へ 06/26 17:33
- 勝ち点並ぶドイツと米国が対戦 06/26 17:22
- マリナーズ岩隈が4敗目 06/26 14:38
- 米移籍の加地が記者会見 06/26 12:05
- ヤンキースの黒田が5勝目 06/26 11:57
- 【W杯コラム】余裕の引き分け 06/26 11:41
- 韓国、アジア勢1勝目指す 06/26 10:27
- 伊達組、青山組が2回戦へ 06/26 09:31
- リンスカムが無安打無得点 06/26 08:59
- エクアドル0―0フランス 06/26 08:22
- ホンジュラス0―3スイス 06/26 08:08
- ボスニア3―1イラン 06/26 03:50
- ナイジェリア2―3アルゼンチン 06/26 03:45
6月25日
- テニス、奈良、土居は2回戦敗退 06/25 21:44
- D2―4日(25日) 06/25 21:38
- W杯かみつき騒動、企業が便乗 06/25 21:20
- W杯、日本に「落胆」とドイツ誌 06/25 20:41
- 米―独は緊張感ある攻防に 06/25 19:53
- ゴルフ、佐藤が暫定首位 06/25 19:18
- ゴルフ、横峯「アグレッシブに」 06/25 17:43
- アルゼンチンが最終戦 06/25 16:16
- 【W杯コラム】これが日本の実力 06/25 11:48
- 川崎は3打数1安打 06/25 11:36
- 【W杯コラム】母国の前途は多難 06/25 11:13
- ザッケローニ監督、去就明言せず 06/25 10:06
- サッカーの内田、代表引退を示唆 06/25 09:40
- 川崎は1安打、イチロー出場せず 06/25 09:34
- ギリシャ2―1コートジボワール 06/25 08:51
- 全英テニス26歳伊藤1回戦敗退 06/25 08:38
- 日本1―4コロンビア 06/25 07:50
- イタリア0―1ウルグアイ 06/25 04:20
- コスタリカ0―0イングランド 06/25 04:16
6月24日
- 選手強化へ銃刀法緩和を要望 06/24 22:03
- 都知事、カヌー以外まだ指示せず 06/24 20:31
- DF加地亮がチバスUSAへ移籍 06/24 19:41
- レスリング代表に松本、高谷兄弟 06/24 18:17
- 野球、12U代表監督に仁志氏 06/24 18:12
- 東京五輪準備、25日から初会合 06/24 17:47
- 野球のBCリーグ来春から8球団 06/24 16:53
- 伊―ウルグアイが最終戦 06/24 16:40
- 中止のプロ野球 06/24 16:28
- パウエル、パリ国際出場へ 06/24 16:13
- メッシ、3連続得点なるか 06/24 15:39
- フランス、攻撃陣に勢い 06/24 15:21
- コートジボワール「歴史つくる」 06/24 14:27
- 【W杯コラム】首位を取る戦い 06/24 11:44
- 川崎、イチローともに1安打 06/24 11:38
- 大リーグ、川崎が1安打1得点 06/24 11:33
- 【W杯コラム】考えない大切さ 06/24 11:14
- コロンビア「日本スピードある」 06/24 10:27
- テニス、ジョコビッチが2回戦へ 06/24 09:12
- クロアチア1―3メキシコ 06/24 08:53
- カメルーン1―4ブラジル 06/24 08:22
- W杯、ランパードらが先発へ 06/24 06:17
- FIFA、賀川氏を紹介 06/24 05:56
- W杯、「弱点突く」とスアレス 06/24 05:07
- スペイン3―0豪州 06/24 03:49
- オランダ2―0チリ 06/24 03:40
6月23日
- 仮設の水球会場も見直しへ 06/23 22:41
- クルム伊達、初戦敗退 06/23 22:23
- 来年3月の横浜マラソン要項発表 06/23 22:07
- ラグビー日本が過去最高の10位 06/23 20:32
- 競輪・武田らの自粛期間3カ月に 06/23 20:10
- 交流戦削減案は結論出ず 06/23 19:44
- J2千葉、鈴木監督を解任 06/23 19:32
- 国内最高峰の大会を新設 06/23 19:23
- ボクシング高山4団体制覇に意欲 06/23 19:02
- コロンビア戦の見どころ 06/23 18:39
- W杯、コロンビア戦の見どころ 06/23 18:17
- 大学生のパワーを東京五輪に 06/23 18:14
- ウィー7位、横峯39位に 06/23 18:06
- W杯、ベルギー3大会ぶり16強 06/23 18:03
- 9月に八重樫と井上がW防衛戦 06/23 17:41
- ゴルフ、松山は14位で変わらず 06/23 17:09
- W杯、オランダとチリが対戦へ 06/23 16:46
- 競泳、米レデッキーがまた世界新 06/23 16:40
- 米シニアゴルフ、レーマンが優勝 06/23 16:13
- 米ゴルフ、ストリールマンが優勝 06/23 13:46
- 女子テニス世界ランク奈良41位 06/23 12:08
- 【W杯コラム】快勝で悲願に前進 06/23 11:48
- 【W杯コラム】若手が再び躍動 06/23 11:44
- 柔道、田知本と西山が優勝 06/23 10:54
- ブラジル、カメルーン戦へ緊張感 06/23 10:38
- W杯スペイン、カシリャス外す 06/23 10:30
- 米国2―2ポルトガル 06/23 09:48
- Rソックスの上原が3勝目 06/23 09:25
- リオ競技場、警備強化 06/23 09:21
- 【速報】米とポルトガルは2―2 06/23 09:01
- 松井秀喜氏がOB行事参加 06/23 08:43
- 韓国2―4アルジェリア 06/23 07:55
- W杯、日本はコロンビア戦へ調整 06/23 07:42
- ヤンキース田中将が2敗目 06/23 06:54
- 【速報】アルジェリアが勝つ 06/23 05:58
- ブルージェイズ川崎は無安打 06/23 05:18
- カブス和田がメジャー契約 06/23 05:12
- ベルギー1―0ロシア 06/23 03:48
6月22日
- ゴルフ、ウィーがメジャー初優勝 06/22 23:30
- F1、小林16位 06/22 23:06
- 猫ひろしさん、アジア大会出場へ 06/22 21:49
- 元幕内皇風が断髪式 06/22 19:48
- ベルギーがロシア戦 06/22 19:33
- 男子200平、小関がV 06/22 18:56
- 卓球荻村杯、石川と水谷は準優勝 06/22 18:46
- オートレース、永井が5度目優勝 06/22 18:31
- オランダ―チリは1位争い 06/22 17:58
- ヤ4―3オ(22日) 06/22 17:57
- 巨10―5ソ(22日) 06/22 17:56
- 神1―5楽(22日) 06/22 17:52
- ゴルフ、竹谷がツアー初優勝 06/22 17:34
- 楽天・美馬が危険球退場 06/22 16:20
- マリー「最高の準備」と自信 06/22 15:29
- 男子テニス、ロペスが連覇 06/22 13:54
- ブダペスト柔道大会、松本ら優勝 06/22 12:42
- 【W杯コラム】満足な引き分け 06/22 12:04
- 【W杯コラム】最後は個の力 06/22 11:36
- 米男子ゴルフ、ムーアが単独首位 06/22 10:44
- ナイジェリア1―0ボスニア 06/22 10:01
- 全米女子OP、横峯は5打差7位 06/22 09:52
- Rソックス田沢1回1/3無失点 06/22 09:23
- 【速報】ナイジェリアが勝つ 06/22 09:08
- ブルージェイズの川崎は無安打 06/22 08:27
- ドイツ2―2ガーナ 06/22 06:38
- イチローは4打数1安打 06/22 05:54
- W杯、日本が急きょ練習取りやめ 06/22 05:51
- W杯ベルギー、ロシアが会見 06/22 05:26
- アルゼンチン1―0イラン 06/22 04:03
- ロイヤルズ青木がDL入り 06/22 00:57
- バド、田児が世界1位破り決勝へ 06/22 00:35
6月21日
- F1、マッサが08年以来のPP 06/21 22:42
- 錦織「自信持って戦う」 06/21 22:11
- 神0―4楽(21日) 06/21 21:20
- セ・パ交流戦、22日V決定 06/21 18:27
- ヤ11―3オ(21日) 06/21 18:13
- ゴルフ、竹谷と張棟圭が首位守る 06/21 18:03
- ベルギー勝てば決勝Tへ 06/21 18:02
- 巨1―3ソ(21日) 06/21 17:25
- アルゼンチンがイランと対戦 06/21 17:01
- ラグビー日本、イタリアに初勝利 06/21 16:36
- Rソックス田沢は1/3回無失点 06/21 15:33
- マリナーズの岩隈は5失点 06/21 13:57
- 川崎は3打数2安打 06/21 12:56
- ヤンキースの黒田は6回2失点 06/21 12:42
- ゴルフ、横峯が6打差7位浮上 06/21 10:54
- 【W杯コラム】小国が見せた驚き 06/21 10:53
- 夏の高校野球地方大会が開幕 06/21 10:16
- ホンジュラス1―2エクアドル 06/21 10:14
- 川崎、2安打などで貢献 06/21 10:06
- 石川、今田は予選落ち 06/21 09:41
- 田中将が慈善活動に参加 06/21 09:12
- 【速報】エクアドルが初勝利 06/21 09:01
- W杯、コロンビア戦へ調整再開 06/21 08:51
- メッシ生かすシステムで臨む 06/21 08:36
- ゴルフ、アマ橋本と森田が33位 06/21 07:22
- スイス2―5フランス 06/21 06:36
- 【速報】フランス5得点で2連勝 06/21 05:58
- イタリア0―1コスタリカ 06/21 03:52
- 【速報】コスタリカが決勝T進出 06/21 03:06
- 日本人男性2人を一時拘束 06/21 00:41
6月20日
- 日本代表、ナタルを出発 06/20 23:25
- ヤ6―9ソ(20日) 06/20 22:22
- 錦織圭、世界67位と初戦 06/20 20:12
- 競泳、高橋が400個メで日本新 06/20 19:45
- セ、交流戦12試合制提案へ 06/20 19:26
- ゴルフ、34歳竹谷が首位浮上 06/20 19:20
- 岩手に東京五輪クレー射撃誘致を 06/20 19:11
- 大使のカズがブラジルから帰国 06/20 17:53
- 伊、コスタリカと第2戦 06/20 17:51
- 高校野球、地方大会が21日開幕 06/20 17:11
- 乱入相次ぎW杯の会場警備に不安 06/20 17:08
- 11点5ゲーム制を試行 06/20 17:04
- アルゼンチンの優位動かず 06/20 17:02
- イチローは4打数1安打 06/20 12:43
- 【W杯コラム】なさすぎた勇気 06/20 12:20
- 【W杯コラム】頼れるエース復活 06/20 11:40
- 日本0―0ギリシャ 06/20 09:37
- 米男子ゴルフ第1R、石川76位 06/20 09:37
- W杯ダフ屋行為で2邦人一時拘束 06/20 07:34
- ウルグアイ2―1イングランド 06/20 06:50
- 日本戦開催地で土砂崩れ 06/20 05:41
- ブフォン、出場は当日判断 06/20 05:09
- コロンビア2―1コートジ 06/20 03:55
6月19日
- 森田、橋本が73で暫定35位に 06/19 23:20
- 日本人サポーター、2戦目に期待 06/19 23:05
- JOC、議員に強化態勢維持要望 06/19 21:58
- 卓球・田代、町らが本戦進出 06/19 21:32
- ヤ2―7ソ(19日) 06/19 21:28
- ゴルフ、近藤啓ら6人が首位 06/19 19:35
- パスで崩すイタリア 06/19 19:18
- 競泳、渡部が100平で日本新 06/19 18:38
- マラドーナ氏、W杯に入場できず 06/19 18:28
- 1100億円でIOCと合意 06/19 18:11
- 部内暴力で駒大部長謹慎 06/19 18:00
- 【W杯コラム】やるしかない 06/19 13:03
- 【W杯コラム】チリが熱く突破 06/19 11:56
- 川崎は4打数無安打 06/19 11:40
- 五輪スポーツDに室伏選手起用へ 06/19 11:37
- カメルーン0―4クロアチア 06/19 09:49
- W杯、攻めに自信のイングランド 06/19 09:12
- 田中将、次回登板は23日 06/19 08:47
- ゴルフ、宮里藍グリーン攻略が鍵 06/19 08:42
- コロンビア監督は警戒 06/19 08:15
- W杯、西村氏は第4審判を担当 06/19 08:09
- 西村主審に脅迫的行為、開幕戦後 06/19 08:08
- スペイン0―2チリ 06/19 07:00
- Rソックス上原が2勝目 06/19 05:53
- W杯、空港での窃盗被害相次ぐ 06/19 05:44
- チリのファン乱入、85人拘束 06/19 04:24
- 豪州2―3オランダ 06/19 03:54
- ◎【速報】オランダが競り勝つ 06/19 03:01
6月18日
- 巨5―6オ(18日) 06/18 22:59
- 神0―4日(18日) 06/18 21:29
- 錦織圭、自身最高の第10シード 06/18 19:33
- オリックスの西がトップ浮上 06/18 19:15
- 競泳の北島、山口らが最終調整 06/18 17:51
- W杯、オランダが豪州と対戦 06/18 17:41
- 破壊力ある攻撃のコロンビア 06/18 17:35
- W杯、日本は20日にギリシャ戦 06/18 17:28
- ゴルフ、ツアー選手権19日開幕 06/18 17:04
- ギリシャ戦の見どころ 06/18 16:39
- J2京都バドゥ監督との契約解除 06/18 16:07
- 宮里藍、全米女子10度目の挑戦 06/18 16:03
- ダルビッシュ、7失点で3敗目 06/18 15:27
- イチロー無安打、川崎は1安打 06/18 14:33
- メッツ松坂は1回無失点 06/18 13:38
- 【W杯コラム】サブの活躍で勝利 06/18 12:03
- レッドソックス田沢は1回無失点 06/18 11:33
- メッツ松坂回復、21日先発 06/18 11:15
- W杯観戦に訪れ麻薬密売人御用 06/18 11:07
- 西堀、溝江組は本戦進めず 06/18 10:28
- 100m、9秒86でガトリンV 06/18 10:15
- 田中将1失点で11勝目 06/18 10:11
- ロシア1―1韓国 06/18 09:51
- 【速報】ロシアと韓国は引き分け 06/18 08:58
- 全米女子OPゴルフ、成田が練習 06/18 08:55
- オランダ、初戦から布陣変更も 06/18 08:49
- カズ「好きなことを一生懸命」 06/18 08:18
- ブラジル0―0メキシコ 06/18 06:38
- 【速報】ブラジルは引き分ける 06/18 05:56
- ベルギー2―1アルジェリア 06/18 04:00
- 【速報】ベルギーが逆転勝ち 06/18 02:59
- Bジェイズ川崎がメジャー昇格へ 06/18 00:19
6月17日
- ギリシャ戦の主審が決定 06/17 23:39
- 神4―3日(17日) 06/17 23:04
- チンクアンタ会長を再選 06/17 22:08
- 巨8―0オ(17日) 06/17 21:30
- 野球のアジアSを世界公認大会に 06/17 20:48
- 休養中の星野監督が手術 06/17 20:16
- 日ハム大谷が18日甲子園初登板 06/17 18:55
- 大相撲、時天空が「間垣」取得 06/17 18:27
- 広島の松山、前半戦復帰は絶望的 06/17 17:30
- 戦力整うクロアチア 06/17 17:23
- ベルギーとアルジェリアが対戦へ 06/17 16:02
- W杯で連日徹夜?中国で男性死亡 06/17 15:33
- 瀬戸、競泳欧州GPから帰国 06/17 12:50
- 国立競技場の座席、譲渡始まる 06/17 12:12
- W杯、洪韓国監督が初陣に闘志 06/17 12:03
- 【W杯コラム】際立つ独の充実 06/17 11:55
- 観客席のごみ拾いに称賛の声 06/17 11:34
- Rソックス上原が15セーブ目 06/17 11:27
- J1、C大阪の新監督が初指導 06/17 11:04
- テニス女子、青山組が準々決勝へ 06/17 10:33
- W杯、日本戦開催都市でデモ 06/17 10:26
- W杯、ブラジルはフッキ欠場も 06/17 10:02
- W杯、ベルギー主将が警戒感示す 06/17 10:01
- 最多得点者ジーコ氏も感慨 06/17 09:42
- ガーナ1―2米国 06/17 09:40
- 宮里藍らが公式練習 06/17 09:28
- カズさん「悔いないよう戦って」 06/17 09:06
- 【速報】米国が勝つ 06/17 09:05
- イラン0―0ナイジェリア 06/17 06:35
- 【速報】今大会初の引き分け 06/17 06:01
- ドイツ4―0ポルトガル 06/17 05:14
- 【速報】ドイツ、ポルトに4―0 06/17 03:06
- 元大リーガー、グウィン氏が死去 06/17 01:10
6月16日
- ホッケー日本リーグ再開へ 06/16 23:21
- テニス、守屋と内山が2回戦へ 06/16 23:14
- 女子テニス、奈良は1回戦敗退 06/16 21:15
- 被災地への会場変更「原則無理」 06/16 20:58
- 日本が世界ジュニア柔道開催へ 06/16 20:11
- F1元王者シューマッハー氏退院 06/16 20:07
- 東京五輪、宮城とも連携強化 06/16 19:15
- 全柔連登録、小中学生が大幅減 06/16 19:11
- NHK杯は11月に大阪で開催 06/16 18:56
- 実力者擁するベルギー 06/16 18:27
- ゴルフ、松山は14位に後退 06/16 17:57
- 中国紙、日本代表はパワー不足 06/16 17:17
- C大阪、ペッツァイオリ監督就任 06/16 16:49
- 独とポルトガルが対戦へ 06/16 16:29
- 羽生、町田ら特別強化選手に 06/16 16:08
- ヤンキース田中、次の登板18日 06/16 13:34
- 【W杯コラム】エース後半に輝く 06/16 12:45
- バスケ、スパーズが7季ぶりV 06/16 12:25
- 世界ランク、宮里美が41位 06/16 12:11
- アルゼンチン2―1ボスニア 06/16 09:48
- W杯、GLTがゴール判定助ける 06/16 08:56
- 日本応援団が「ブラジル人魅了」 06/16 08:53
- イチローは4打数2安打 06/16 08:47
- マリナーズ岩隈は5勝目 06/16 08:45
- メッツ松坂が体調不良で降板 06/16 08:29
- Rソックス田沢が初黒星 06/16 08:20
- クリンスマン米代表監督が会見 06/16 08:08
- フランス3―0ホンジュラス 06/16 07:00
- ロイヤルズの青木は出場せず 06/16 06:48
- メッツの松坂は体調不良で降板 06/16 05:49
- スイス2―1エクアドル 06/16 04:14
6月15日
- テニス、イバノビッチが優勝 06/15 23:27
- テニス、奈良組は1回戦敗退 06/15 23:25
- 日本代表がイトゥへ 06/15 23:01
- 吉田、伊調が新階級制す 06/15 20:05
- ドイツ戦の見どころ 06/15 20:04
- ロ5―8広(15日) 06/15 18:24
- オ4―6中(15日) 06/15 17:56
- W杯、両チームの健闘たたえる 06/15 17:49
- 日2―3ヤ(15日) 06/15 17:42
- マラソン、猫さんまた敗れる 06/15 17:31
- 楽2―3巨(15日) 06/15 17:03
- ソ1―5D(15日) 06/15 16:52
- バレーボール、日本は8連敗 06/15 16:43
- 好カードの独―ポルトガル 06/15 16:37
- 全日本大学野球、東海大4度目V 06/15 16:20
- ヤンキース黒田は4失点で5敗目 06/15 15:31
- 【W杯コラム】追い込まれた日本 06/15 15:26
- コートジボワール2―1日本 06/15 12:33
- ザッケローニ監督の談話 06/15 12:15
- 【W杯コラム】楽しみな新星出現 06/15 10:29
- 松山、3Rは74で23位に後退 06/15 09:48
- イングランド1―2イタリア 06/15 09:39
- Rソックス田沢、上原とも無失点 06/15 09:24
- ロイヤルズ青木は5打数1安打 06/15 07:47
6月14日
- 日7―6ヤ(14日) 06/14 22:14
- レスリング、長谷川恒平が優勝 06/14 21:14
- ラグビー、NZと豪州が勝つ 06/14 21:11
- 重量挙げ、三宅や八木らが代表に 06/14 19:54
- 日本、15日W杯1次リーグ初戦 06/14 18:24
- ソ4―2D(14日) 06/14 17:55
- 楽1―3巨(14日) 06/14 17:47
- ゴルフ、工藤が8アンダーで首位 06/14 17:45
- レベル高いスイス 06/14 17:43
- ロ8―4広(14日) 06/14 17:42
- ラグビー、日本代表15日米国戦 06/14 17:33
- 岐阜で中学生がW杯「前哨戦」 06/14 17:31
- 阪神の能見がセ・リーグ新記録 06/14 17:21
- オ7―4中(14日) 06/14 17:06
- W杯代表ユニ、かわいくコーデ 06/14 17:01
- コロンビアがギリシャ戦 06/14 16:53
- 磐田が2連勝 06/14 16:52
- 決勝は神奈川大―東海大 06/14 16:41
- メッシ、実力発揮できるか 06/14 15:33
- 広島の松山外野手が登録抹消 06/14 15:28
- イチローは2安打1打点 06/14 14:38
- NHL、キングズが2季ぶり優勝 06/14 13:49
- ロイヤルズの青木は4打数2安打 06/14 12:53
- 【W杯コラム】最終章の幕開け 06/14 11:55
- W杯、FIFAは西村主審擁護 06/14 10:27
- ゴルフ松山10打差14位に後退 06/14 10:14
- 青木、5連勝に貢献 06/14 09:50
- チリ3―1豪州 06/14 09:49
- W杯、カズがレシフェ入り 06/14 08:37
- W杯、「難しい戦い」と両監督 06/14 08:17
- スペイン1―5オランダ 06/14 06:37
- ベッケンバウアー氏を処分 06/14 04:47
- メキシコ1―0カメルーン 06/14 03:45
6月13日
- クルム伊達は4強入り逃す 06/13 23:37
- 楽8―2ヤ(13日) 06/13 21:52
- 西7―0広(13日) 06/13 21:26
- 女子ゴルフ、森岡が首位発進 06/13 21:07
- 都、五輪カヌー会場の変更検討 06/13 21:06
- 五輪金の羽生選手が凱旋公演 06/13 20:24
- 日本は素早さで勝負 06/13 19:53
- コートジボワール戦の見どころ 06/13 19:52
- レスリング、浜口が右足痛め欠場 06/13 19:15
- 女子ゴルフ、イ・ナリが首位 06/13 19:00
- IH女子代表、新監督に藤沢氏 06/13 18:28
- 大学野球、神奈川大が4強入り 06/13 16:33
- メキシコがカメルーン戦 06/13 15:30
- イチロー、途中出場で1安打 06/13 15:02
- NBA、スパーズがVに王手 06/13 13:05
- 体操の塚原氏、講道館の評議員に 06/13 12:04
- 上原14セーブ目、田沢も無失点 06/13 12:01
- 上原14S、田沢も無失点 06/13 11:50
- 【W杯コラム】急に始まったW杯 06/13 11:39
- 無安打無得点試合の岸を表彰 06/13 11:23
- 男子ゴルフ、松山4打差6位発進 06/13 10:47
- W杯、主審に「勝利奪われた」 06/13 10:45
- W杯14日にスペイン―オランダ 06/13 09:51
- ブラジル3―1クロアチア 06/13 08:48
- W杯日本代表、初戦想定し調整 06/13 08:12
- W杯のブラジルで「おもてなし」 06/13 04:13
- 練習後、W杯決戦の地へ移動 06/13 00:08
6月12日
- テニス、クルム伊達が準々決勝へ 06/12 23:35
- W杯サッカー開幕前に抗議デモ 06/12 23:27
- 松山、13H終え2オーバー 06/12 23:01
- オ9―5D(12日) 06/12 22:22
- 北島選手、競技団体役員に 06/12 22:19
- ソ4―3中(12日) 06/12 22:00
- 日2―11巨(12日) 06/12 21:44
- 西5―4広(12日) 06/12 21:18
- 2017年国体は愛媛に決定 06/12 20:28
- テコンドー、組織改革委を設置 06/12 20:06
- 女子ゴルフ、大江ら3人が首位 06/12 19:21
- メキシコは五輪組が成長 06/12 19:11
- サンパウロにナカタカフェ 06/12 17:57
- イラク小児がん患者らとW杯応援 06/12 17:02
- 全英女子ゴルフに宮里藍、森田ら 06/12 15:22
- ヤンキース田中将、完投で10勝 06/12 14:35
- サッカー、大使の三浦ブラジルへ 06/12 12:37
- NHL、レンジャーズが1勝目 06/12 12:24
- 競泳の入江、瀬戸らが優勝 06/12 11:34
- 五輪連覇柔道王者に性的暴行疑惑 06/12 10:56
- サンパウロ州でデング熱が流行 06/12 09:31
- FIFAブラッター会長立候補へ 06/12 09:28
- W杯、注目のY・トゥーレら調整 06/12 08:50
- 青木は4打数1安打 06/12 06:50
6月11日
- 出場選手75%が欧州クラブ在籍 06/11 23:31
- オ8―5D(11日) 06/11 21:59
- 日1―2巨(11日) 06/11 21:56
- ソ4―7中(11日) 06/11 21:53
- 村田諒太が世界13位に 06/11 21:40
- バスケ和歌山が経営陣一新 06/11 20:07
- 必勝期すブラジル 06/11 18:27
- 日本のW杯1次突破確率56% 06/11 17:39
- 平木さん、テニス協会常務理事に 06/11 17:15
- W杯対戦国の料理、給食に 06/11 16:29
- マリナーズ岩隈は3失点で3敗目 06/11 14:36
- 松坂は6回投げ3勝目 06/11 14:14
- NBA、スパーズが2勝目挙げる 06/11 13:26
- Rソックス上原が13セーブ目 06/11 13:14
- ロイヤルズの青木は出場せず 06/11 13:01
- 日本はベスト16予想が最多 06/11 12:48
- ブラジル開幕戦勝利を“予言” 06/11 10:49
- 岡田前監督が日本にエール 06/11 10:10
- コートジボワール、攻撃陣を警戒 06/11 10:05
- 米で松井氏がOB行事に初参加 06/11 09:50
- サッカーW杯、日本代表は休養 06/11 09:37
- 全米ゴルフ前に練習ラウンド 06/11 08:18
- サッカー日本代表練習近くで殺人 06/11 01:26
6月10日
- サッカー、ザック監督が記者会見 06/10 22:44
- 女子テニス、奈良は1回戦敗退 06/10 21:41
- JOCが3年ぶり赤字、6億円 06/10 21:17
- 竹田会長「強化するのはJOC」 06/10 20:58
- サンパウロの建設現場で死亡事故 06/10 19:34
- 高校野球地方大会、21日開幕 06/10 17:30
- 広島・前田、12日の先発回避 06/10 17:15
- FIFA研究グループに宮本氏 06/10 16:27
- W杯スキー、秋田でモーグル開催 06/10 16:14
- サッカー、ガーナが韓国に大勝 06/10 13:27
- NHL、キングズが3連勝で王手 06/10 12:25
- イチロー、青木は降雨で試合中止 06/10 10:16
- W杯前に出場国国連大使がエール 06/10 09:41
- 被災生徒がサッカーW杯観戦 06/10 09:37
- W杯初導入のゴール判定技術 06/10 09:16
- 松山、開催コースで調整 06/10 08:57
- 宮里美40位、森田41位 06/10 05:32
6月09日
- クルム伊達が2回戦へ 06/09 22:20
- 中2―5日(9日) 06/09 22:06
- スタンリッジ投手が全球団勝利 06/09 21:52
- 神0―6ソ(9日) 06/09 21:39
- D0―10楽(9日) 06/09 21:28
- プレミア12の日本開催断念 06/09 20:23
- インドネシアでの試合延期 06/09 19:59
- 男子ゴルフ、松山13位変わらず 06/09 18:45
- 23歳MFのカルボネロを招集 06/09 18:37
- J2札幌の小野「J1に昇格へ」 06/09 18:35
- バレー、堺の新監督に印東氏 06/09 18:29
- W杯日本代表ユニホームが絶好調 06/09 18:22
- ブラジルで空のトラブル相次ぐ 06/09 17:19
- アジア大会代表に桐生、山県ら 06/09 16:46
- ユース五輪に山崎、久保埜 06/09 16:19
- テニス錦織、12位に下がる 06/09 16:10
- NBA決勝、ヒート勝ち1勝1敗 06/09 12:09
- ビーチバレー西堀、溝江組は4位 06/09 11:43
- サッカー親善試合、フランス大勝 06/09 11:21
- ウルグアイへの雪辱を熱望 06/09 11:18
- C大阪、ポポビッチ監督を解任 06/09 10:38
- 今田は通算2オーバーの50位 06/09 10:30
- ゴルフ野村45位、上原は67位 06/09 09:58
- ホッケー女子W杯、日本は3敗目 06/09 09:25
- 香港に5mのキャプテン翼像登場 06/09 09:06
- F1、リカルドが初優勝 06/09 08:31
- 黒田4敗目、イチロー2安打 06/09 06:29
- 安藤得点するも優勝逃す 06/09 00:55
6月08日
- W杯日本代表、歓迎セレモニー 06/08 23:30
- W杯カメルーン代表が搭乗拒否 06/08 22:47
- 京大、41年ぶり大学駅伝出場 06/08 22:38
- ボクシング、コットが4階級制覇 06/08 19:18
- レアンドロドミンゲス獲得 06/08 19:15
- 桐生、10秒22で初優勝 06/08 18:34
- 神14―8ソ(8日) 06/08 18:29
- 中0―6日(8日) 06/08 18:03
- D5―1楽(8日) 06/08 17:31
- シンクロ、チームの日本が優勝 06/08 17:13
- 米女子サッカー、川澄がフル出場 06/08 16:56
- 親善試合で領土主張の横断幕 06/08 14:05
- NHL、キングズ逆転で2連勝 06/08 13:22
- ロイヤルズ青木は1安打1打点 06/08 12:33
- ロナルドが練習復帰 06/08 11:36
- 米男子ゴルフ、今田は通算+2 06/08 11:06
- サッカー親善試合でスペイン白星 06/08 11:01
- ブラジルのリオ、五輪批判に反論 06/08 10:34
- FIFA、調査報告書待って対応 06/08 10:23
- 自動車のF1、ロズベルクがPP 06/08 09:38
- サッカー女子、熊谷のリヨン2冠 06/08 09:30
- 米女子ゴルフ、野村は43位後退 06/08 08:44
6月07日
- 日本代表、ブラジルへ向け出発 06/07 23:01
- ホッケー協会、会長ら8人解任 06/07 21:21
- J2、首位の湘南が2連勝 06/07 21:09
- 桐生は10秒15で準決勝へ 06/07 19:37
- スケート羽生、郷さんの歌で熱演 06/07 19:29
- 中6―3楽(7日) 06/07 18:40
- 体操、女子は18歳笹田が初V 06/07 18:22
- 手嶋が首位、1打差に小田孔 06/07 18:07
- シンクロ、乾が首位で決勝へ 06/07 17:53
- 神1―4オ(7日) 06/07 17:50
- 大鵬の生誕地サハリンに銅像を 06/07 17:19
- 中止のプロ野球 06/07 14:53
- イチローは4打数1安打 06/07 12:47
- バスケ富樫、NBA挑戦へ渡米 06/07 12:33
- 日本勢は男女で決勝Tへ 06/07 12:31
- サッカー、ブラジルや独が勝つ 06/07 12:29
- ゴルフ、松山はスピースらと同組 06/07 11:54
- 日本4―3ザンビア 06/07 11:27
- W杯、西村主審ら最後の研修 06/07 11:15
- 今田、悪天候で第2R終了できず 06/07 10:42
- サンパウロ、地下鉄スト駅で衝突 06/07 09:36
- 米女子ゴルフ、野村19位に後退 06/07 09:31
- 国際スキー連盟、新理事に村里氏 06/07 05:57
- 自転車の松本総監督を解任 06/07 02:07
- サッカー、リベリが腰痛で欠場 06/07 00:54
- 札幌、サポーター無期限入場禁止 06/07 00:33
6月06日
- ジョコビッチ、2年ぶり決勝進出 06/06 23:08
- 神3―4オ(6日) 06/06 22:21
- 中5―1楽(6日) 06/06 21:26
- ゴルフ、未勝利の大田和が首位 06/06 19:22
- 東京五輪会場にロープウエー 06/06 19:18
- シンクロ、乾・三井組が首位 06/06 18:53
- NHK杯、復調の内村ら意気込み 06/06 18:04
- 野球「育成功労賞」49人を発表 06/06 17:24
- W杯にレアルから12人登録 06/06 16:03
- 5月の月間MVP、井納らが受賞 06/06 15:52
- NBA決勝、スパーズが先勝 06/06 13:19
- ロイヤルズ青木は1安打1打点 06/06 12:09
- ゴルフ、悪天候で60人終了せず 06/06 11:36
- ギリシャ新監督はW杯後に発表 06/06 11:20
- サッカー日本代表応援車お披露目 06/06 10:23
- 18~19年の世界選手権決定 06/06 10:14
- 米女子ゴルフ、野村6位と好発進 06/06 10:03
- W杯、予定通り12会場で開催 06/06 10:00
- 男子100、米のガトリンが制す 06/06 09:46
- 米ドラフト全体1位は高校生左腕 06/06 09:44
- バスケ日本、初日は1勝2敗 06/06 09:05
- サッカー日本、7日にザンビア戦 06/06 08:58
- 全仏テニス、ハレプが決勝進出 06/06 06:09
- ヤンキース田中将が9勝目 06/06 05:46
- シャラポワ逆転で決勝へ 06/06 00:58
- 白鵬関が第4子の流産公表 06/06 00:14
県内過去のニュース
- 2014年04月
- 2014年03月
- 2014年02月
- 2014年01月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年07月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年04月
- 2013年03月
- 2013年02月
- 2013年01月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年09月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月
- 2012年02月
- 2012年01月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2011年02月
- 2011年01月
共同特集
週間ランキング
関連サイト
- 共同購入クーポンサイト「Q-tokuおおいた」
- 折込広告センター(株)
- 動画サイト「oitatv.com」
- 大分の情報なら「oita-portal.com」
- 47CLUB(よんななクラブ)
- 学生のための就活支援サイト「OPASS」
- 別府・大分住宅情報「SEARCH」
- 住まいの情報誌「WISE」
- 大分ママのコミュニティ「大分ママネット」
- アイぶんぶんひろば
- おおいたの観光情報
- NAN-NAN(ナンナン)
- めばえ教室
- 大分合同新聞文化センター
- シティ情報おおいた
- おおいたインフォメーションハウス
- 大分で結婚式を挙げるなら「ハピマリ」
- デジタルバンク
- プランニング大分
- ネットで見るチラシ「アイチラシ」
- 九州温泉プレス
- ほめられサロン
- ありがとサロン
- おおいたランチ
※無断転載を禁じます。 当ホームページに掲載の記事、写真等の著作権は大分合同新聞社または、情報提供した各新聞社に帰属します。
![]()